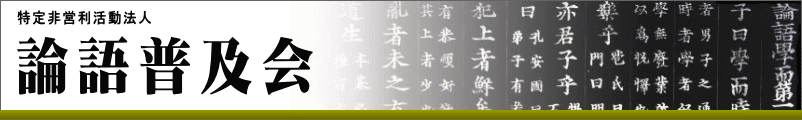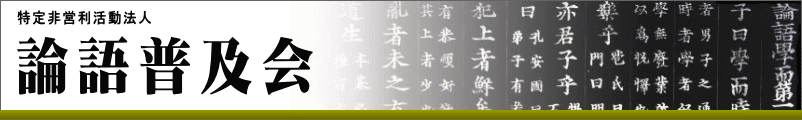| 今月の論語 (2025年11月) |
|
猶恐失之(ゆうきょうしつし))
子(し)曰(のたま)わく、
學(がく)は及ばざるが如くするも、
猶(なお)之(これ)を失わんことを恐る。
子曰、學如不及、猶恐失之。
(泰伯第八、仮名論語一〇六頁)
|
|
〔注釈〕先師が言われた。「学問は常に及ばないような気持ちで求めてゆくが、なおその気持ちを失いはしないかと恐れる」
〔和歌〕とつおいつ 追はれつ逃ぐる 人のあと 追ふにも似たる わが學の道
(見尾勝馬)
会長 目黒泰禪
十月六日、仲秋の名月は実にくっきりと美しかった。これまでと違い、つい月面の墨絵のような兎の耳に目がとまってしまう。
この夏は酷暑のため家内も私も家に籠る日々が続いた。これまでの積読(つんどく)本や最近入手した本など読書漬けの毎日となり、フレイルがさらに進んだ。読んだのは年来の四書五経から離れた小説の類が多かったが、読書量も読解力もかなり落ちていた。体力と記憶力の衰えは如何ともしがたい。それでも『論語』の泰伯篇にある「学問は常に及ばないような気持ちで求めてゆくが、なおその気持ちを失いはしないかと恐れる(猶恐失之(ゆうきょうしつし))」と、心の駒に鞭打っての夏であった。
クーラーを効かせながら読んだ中の一冊、三島由紀夫最後の作品『豊饒の海』四部作、その第三巻「暁の寺」には次の記述がある。
……西暦紀元四世紀をすぎるころから、インドにおける仏教は急速に衰退した。いみじくも言われているように、「ヒンズー教がその友愛の抱擁によって仏教を殺した」のである。ユダヤにおけるキリスト教とユダヤ教、支那(しな)における儒教と道教の間柄のように、インドでも亦(また)、仏教が世界的な宗教になるためには、その母国をより土俗的な宗教の支配に委(ゆだ)ねて、一旦(いったん)そこから放逐されなければならなかった。……
この小説の主人公本多を通して、インドや西洋の輪廻転生説が詳細に語られる。さらには、仏教が否定した我(アートマン)と仏教が継受した業(カルマ)との矛盾からの帰結として阿頼耶識(あらやしき)が語られる。小説は小説としてそのまま読みすすめればそれでいいのだが、「学問は常に及ばないような気持ちで求めてゆきたい」と、インド哲学者中村元の原始仏教や興福寺貫首多川俊映の唯識(ゆいしき)についても改めて読んだ。本多が語るディオニュソス信仰の解説のお蔭で、立花隆著『エーゲ 永遠回帰の海』の理解もさらに深まった。亡くなられた一〇一歳の伊與田覺先生の長寿にはとどかなくても九十一歳の村下好伴先生の年齢までは頑張り、「猶恐失之」の気概で学んでいきたいものである。
四部作の第一巻「春の雪」の末尾に三島自身が、後註―『豊饒の海』は『浜松中納言物語』を典拠とした夢と転生(てんしょう)の物語であり、因(ちな)みにその題名は、月の海の一つのラテン名なる
Mare Foecunditatis の邦訳である、と記している。玉兎の上の耳がその「豊饒の海」である。
|
|